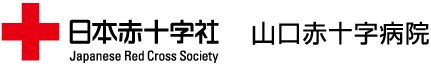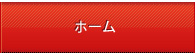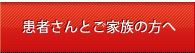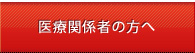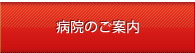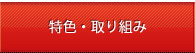緩和ケア内科
主な対象疾患
「がん」と「がん治療」に伴う痛みや吐き気といった不快な症状や、気持ちの辛さ、不眠などが対象となります。
末期心不全に伴う症状にも対応しますが、緩和ケア病棟への入院はがんと診断されている患者さんが対象となります。
概要
「緩和ケア」というと「がんで最期が近い患者さん」が対象で、「入院すると退院できない病棟」と誤解されている方がまだまだ多いのが現状です。ですが、「がん」と診断された時から緩和ケアを導入することで生活の質が改善し、予後も長くなることが明らかとなり、現在では「早期からの緩和ケア」が厚生労働省からも推奨されています。また、緩和ケアは患者さんをサポートすることが大きな役割なので、最近では「支持療法科」と名称変更している医療機関もあります。
当院緩和ケア内科では治療中は緩和ケアチームや外来で、入院が必要な時は緩和ケア病棟で症状緩和やケアに柔軟に対応します。もちろん患者さんの過ごしたい場所で穏やかに暮らして頂くことが一番の目標なので、それぞれのご希望に添ったサポートを行います。
緩和ケア病棟
緩和ケア病棟ではがんと診断された患者さんの痛みをはじめとしたあらゆる症状に、専門的な緩和ケアを提供します。がんそのものに対する抗がん剤治療や手術は行いませんが、症状緩和のための処置や放射線治療などを併用することがあります。また、音楽療法やリハビリテーション、栄養相談の提供も行ないます。
つらい症状が落ち着けば退院を調整しますが、病状悪化時は再入院が可能です。ご家族の休息が必要な場合にはレスパイト(小休止)目的の1-2週間程度の短期入院もご利用頂けます。ご自宅への退院が難しい場合は、ソーシャルワーカーを含むスタッフがご本人、ご家族と相談しながら療養場所を検討していきます。
入院を検討されている方へ
必要時に入院出来るよう登録が必要となりますので、ご本人とご家族に入院相談外来を受診して頂いております。ご本人の来院が体調などにより難しければご家族や代理人のみの来院でも構いませんが、別途相談料(11,000円 税込)が発生します。
受診に際しては以下の書類をお読みになった上でご予約の上、紹介状など必要な書類を揃えてご来院下さい。ご希望の方は病棟見学も可能です。
※当院に通院中の方は、主治医にご相談下さい。
緩和ケア病棟の面会についてはこちらをご確認ください。
必要時の入院対応をご希望される医療機関の皆様へ
ご家族・ご本人に入院相談外来を受診頂きますが、ご紹介に際しては以下の書類をお読みになった上で、必要事項については事前に患者さんにお伝え願います。
当院緩和ケア内科外来への移行や併診をご希望される場合は、その旨も記載頂けますと幸いです。
緩和ケア内科外来
「がん」と「がん治療」に伴う痛みや吐き気といった不快な症状や、気持ちの辛さ、不眠などがあり、通院が可能な方が対象となります。予約制となっており、病状や経過を記載した紹介状が必要になります。主治医や通院先医療機関のスタッフに受診の希望をお伝え下さい。
※当院に通院中の方は、主治医にご相談下さい。
緩和ケアチーム
緩和ケア病棟以外の一般病棟に入院されている方を対象として、主治医や病棟スタッフからの依頼に基づいて「緩和ケアチーム」が介入します。チームには、身体をみる医師、心をみる医師、看護師、薬剤師、音楽療法士、理学療法士、管理栄養士が参加しています。患者さんの症状を和らげるべく、多職種のメンバーが協力して対応します。
※入院中に介入をご希望の方は、病棟スタッフに依頼下さい。
緩和ケア病棟紹介
エントランス
デイルーム
病室(差額なし)
病室(日額6,930円 税込)
病室(日額11,350円 税込)
リフトバス
家族室
医師紹介
河野 友絵 緩和ケア内科副部長
日本内科学会認定内科医
日本緩和医療学会認定医
埼玉県緩和ケア医師研修会修了
山田 健介 緩和ケア内科医師
日本外科学会外科専門医
日本消化器外科学会消化器外科専門医
日本臨床腫瘍学会がん薬物療法専門医